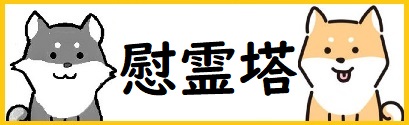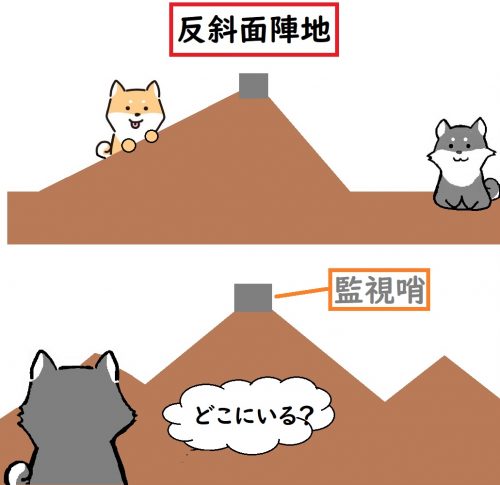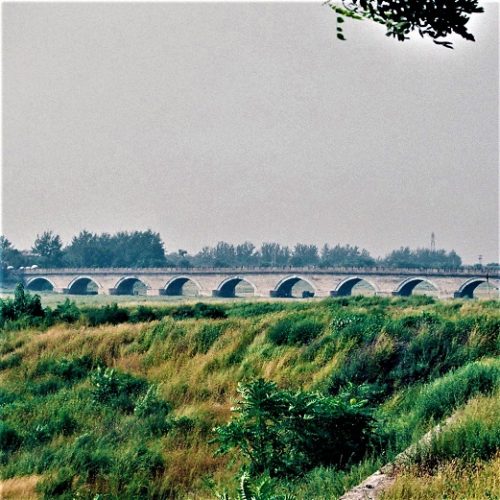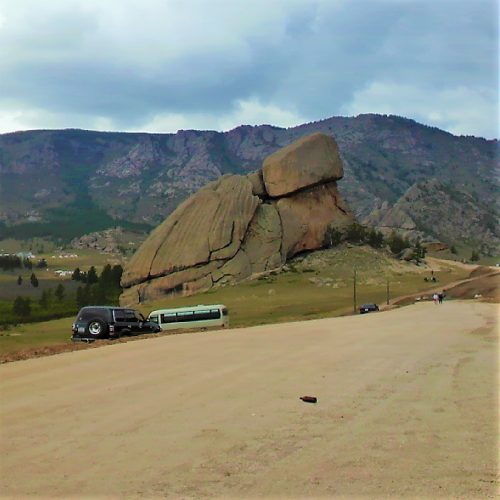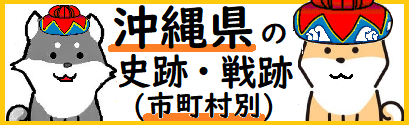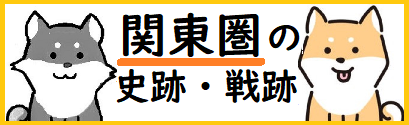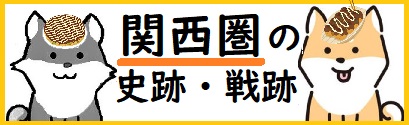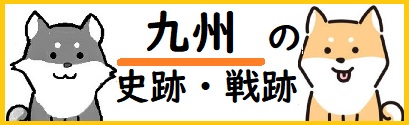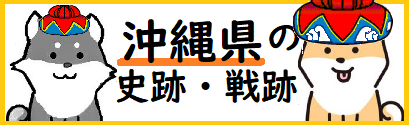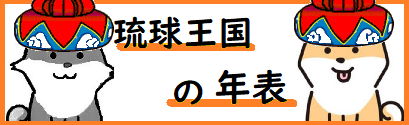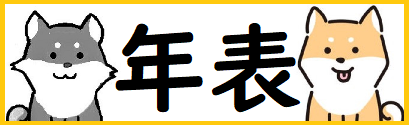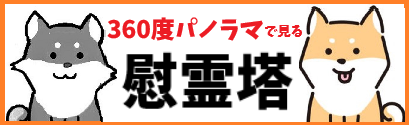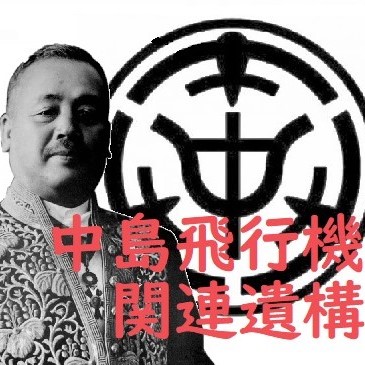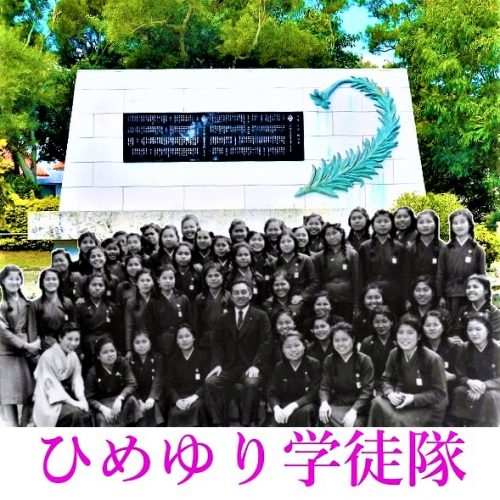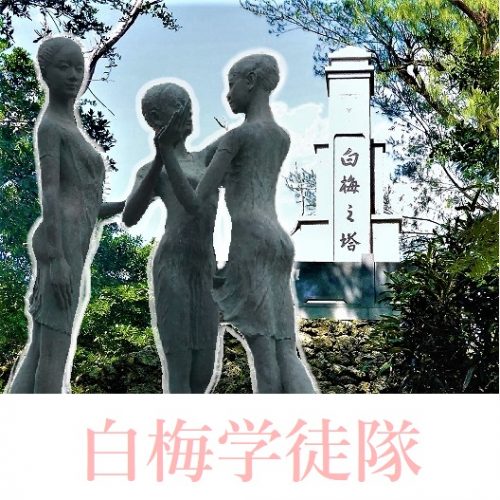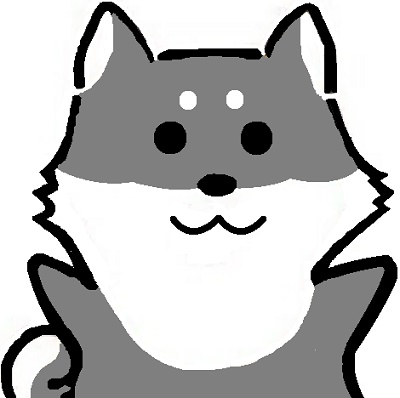
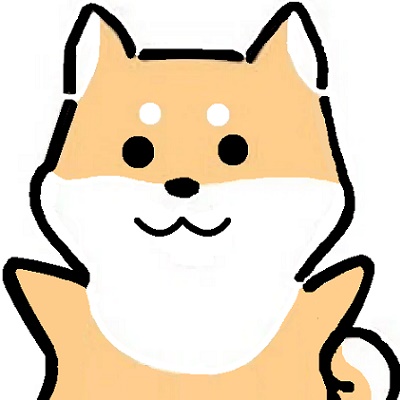
✅名称の法則
大正10年~昭和3年まで→年号を頭に付ける
例:大正10年採用の艦上戦闘機「10式艦上戦闘機」
例:昭和3年採用の艦上戦闘機「3式艦上戦闘機」
昭和4年~昭和15年まで→皇紀(紀元)の下2桁を頭に付ける
皇紀とは、日本の初代天皇「神武天皇」が即位したとされる年を元年とする方式。
皇紀元年は、西暦よりも660年前であるので、西暦1年(元年)は皇紀で表せば皇紀661年となります。
この記事を書いたのは西暦2019年なので、皇紀に直すと「皇紀2679年」といった具合になります。
例:1929年(昭和4年・皇紀2589年)採用の艦上攻撃機「89式艦上攻撃機」
例:1932年(昭和7年・皇紀2592年)採用の艦上攻撃機「92式艦上攻撃機」
例:1939年(昭和14年・皇紀2599年)採用の艦上爆撃機「99式艦上爆撃機」
昭和15年~昭和18年まで→皇紀の下一桁目を頭に付ける
例:1940年(昭和15年・皇紀2600年)採用の艦上戦闘機「零式艦上戦闘機」
例:1941年(昭和16年・皇紀2601年)採用の陸上攻撃機「1式陸上攻撃機」
昭和18年以降→固有名詞を付ける
「〇風」→艦上/水上戦闘機【烈風】
「〇電」→単発局地戦闘機【紫電・紫電改・雷電・震電】
「〇雷」→双発局地戦闘機【天雷】
「〇光」→夜間戦闘機【月光】
「〇雲」→艦上/水上偵察機【彩雲・瑞雲】
「〇山」→艦上/陸上攻撃機【天山・連山】
「〇星」→単発爆撃機【彗星】
「〇海」→哨戒機【東海】
「〇花」→特攻機【桜花・橘花】
「星座名」→双発爆撃機【銀河】
「草木名」→練習機【紅葉・白菊】
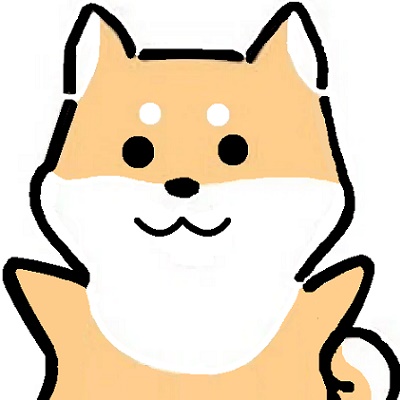
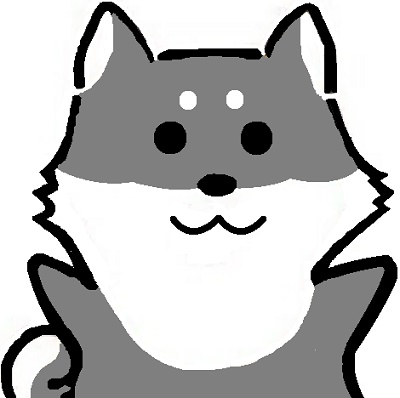
✅機体略号
A6M2(零式艦上戦闘機21型)
【A】1文字目→機種を表すアルファベット
【6】2文字目→その機種で何番目に計画・試作されたか
【M】3文字目→設計会社(メーカー)
【2】4文字目→モデルチェンジの回数
✅機種を表すアルファベット
【A】艦上戦闘機
【B】艦上攻撃機
【C】偵察機
【D】艦上爆撃機
【E】水上偵察機
【F】観測機
【G】陸上攻撃機
【H】飛行艇
【J】陸上戦闘機
【K】練習機
【L】輸送機
【M】特殊攻撃機
【N】水上戦闘機
【P】爆撃機
【Q】哨戒機
【R】陸上偵察機
【S】夜間戦闘機
✅設計会社のアルファベット
【M】三菱重工業
【N】中島飛行機
【A】愛知航空機
【H】広海軍工廠
【K】川西航空機
【W】九州飛行機
【G】日立重工業
【I】石川島重工業
【P】日本飛行機
【S】佐世保海軍工廠
【Y】横須賀海軍工廠
【Z】美津濃
【Si】昭和飛行機
零式艦上戦闘機21型の機体略号は【A6M2】です。
これを例にすると、
【A】は「艦上戦闘機」という機種
【6】は「艦上戦闘機」の中で6番目に設計や試作された
【M】はメーカーである「三菱重工業」
【2】は零式艦上戦闘機で2番目の改修機
であることを表しています。
夜間戦闘機「月光」は【J1N1-S】といった少し違う形をしているのは、「月光」は元々は陸上双発戦闘機という機種で開発されたものでしたが、性能面など様々な面で冷遇され、最終的には「斜銃」を着けて夜間の迎撃で活躍したことから「-S」という変わった記号をしています。
似たようなものとして、二式水上戦闘機【A6M2-N】があります。
零式艦上戦闘機と似た記号であるのは、零式艦上戦闘機をベースとして水上戦闘機に改造したものであるためで「-N」が付いています。